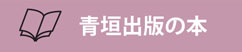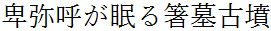 | ||||||||||
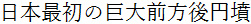 | ||||||||||
| 弥生時代終末期。3世紀に入ると三輪山のふもとに、都市が建設されました。「女王が都とした邪馬台国」ではないかと言われる纒向遺跡である。大阪湾から大和川を遡上して、荷物を積んだ船が行き来しました。都市には立派な運河が建設されました。
そして、3世紀の中頃に突然、巨大な前方後円墳が出現します。それが箸墓古墳です。 箸墓以前の最大級墳墓である「纏向石塚古墳」が長さ90mであるのに対して、箸墓古墳は280m。全国11位の大きさで、その後350年にわたって墳長200m台以上という規模が大王墳のスタンダードとなった。 ある調査では、動員された労働力は、纏向石塚古墳が4万5000人(盛り土は1万㎥)に対して箸墓古墳は135万人(30万㎥)と桁違い、実に30倍の規模なのです(1日2,000人と推計)。 出土した土器を炭素14年代法で調べたところ、箸墓古墳がつくられたのは西暦240年~260年。 女王卑弥呼が没したのは248年頃。まさにピッタリと符合します。 | ||||||||||
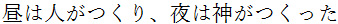 | ||||||||||
| 宮内庁は、箸墓古墳に葬られているのは第7代孝霊天皇の皇女・倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそひめのみこと)であると定めています。
「倭迹迹日百襲姫命」とは、一体どのような女性なのでしょう? 日本書紀によると、彼女は第7代孝霊天皇の皇女なのですが、あの有名な「神婚伝説」が残されています。 | ||||||||||
| 日本書紀「崇神天皇十年ノ条」
倭迹迹日百襲姫命は大物主神と結婚したが、神は夜だけ訪れる。ある夜、倭迹迹日百襲姫命は翌朝もいてほしいと懇願する。それに応じた神が翌朝見せた姿は、小さな蛇であった。彼女は思わず驚愕の声を上げ、その時箸が彼女の「陰部」に刺さって死んでしまう。 そして「大市」に葬られる。人はその墓を名づけて「箸墓」という。この墓は「昼は人がつくり、夜は神がつくった」。 人々はこう歌った。大坂山の石を手越(たごし)で運んだ… |  |
|||||||||
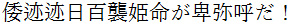 | ||||||||||
| 最初にこう主張したのは、徳島県出身の笠井新也(1884~1956)です。考古学雑誌で4編の論文を発表。
第1回は大正11年(1922)だというから、実に100年前のことです。 〔笠井の論文趣旨は、次の通りです〕
| ||||||||||
| 【アクセス】
桜井市箸中 JR万葉まほろば線「巻向駅」 徒歩15分 |
||||||||||